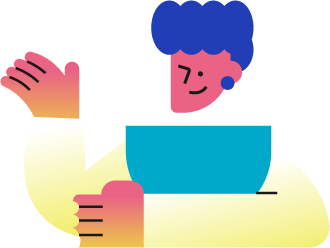ARTICLES
記事
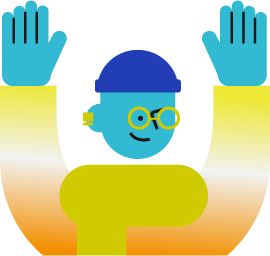
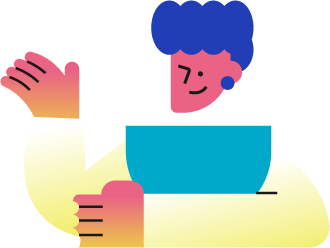
“終わり”と向き合うイベント「終わりのはじめかた」をTBWA HAKUHODO、むじょう、佛現寺と共にQUESTIONで開催しました。

2024年5月20日(月)、21日(火)の2日間、世の中でタブーとされてきた「終わり」に向き合うイベント「終わりのはじめかた」を佛現寺(京都市中京区)とQUESTIONで開催しました。
本イベントは、TBWA\HAKUHODOのオープンイノベーションプロジェクト「Disruption® Lounge」の第四弾です。
今回は、死・終わり・撤退などの「終わり」に向き合ってきた、株式会社むじょう、そして、生活者にとって難しいと感じる仏教の教えにより親しみを感じてもらう取り組みを行っている佛現寺、京都で人・事業・地域をつなぐ取り組みを行っているコミュニティ・バンク京信が共創パートナーとして参画しました。
今回のラウンジのテーマは「終わりのはじめかた」。
世の中でタブーとされてきた「終わり」と向き合うべく、5月20日(月)と21日(火)の2日間にわたり展示会「拝啓、柩(ひつぎ)の中から展」を佛現寺とQUESTIONにて開催。さらに21日(火)にはQUESTIONにてトークセッション「主文、終わりのはじめかた」を開催しました。
本格的な人口低減社会に突入し、世界に先んじて多くの「終わり」を迎えなくてはいけない日本において、企業や地域あるいは個人はこの潮流にどう向き合っていくのか。世界の捉え方を新たにする可能性を秘めた「終わり」の姿を、多くの「終わり」をはじまりに変えて1000年以上の歴史を保ち続けてきた京都から探りました。
「拝啓、柩(ひつぎ)の中から展」

「拝啓、柩(ひつぎ)の中から展」は、本物の棺桶に入り、「自身の終わり」に想いを馳せる体験型展示です。ただ棺桶の居心地を体験するのではなく、推定余命を算出する「余命時計」、死に関する解像度をあげる六つの質問シート「六問銭」を経て、死を意識した状態で棺桶に入り、自らの死やその日までの生き方に思いを馳せる時間を過ごすというものです。「いつ死ぬか分からないからよりよく生きよう」という啓発ではなく、「死ぬこととはどういうことか」を肌で感じ、解像度を上げることがねらいです。

「死」「終わり」という得体の知れない恐ろしい事象に真正面から向き合う仕掛けに、参加者の反応は様々。「意外と怖くなかった」「心が落ち着いた」とほっとしたような顔で棺桶から出てくる方もいれば、沈痛な面持ちで出てくる方も。棺桶の中でそれぞれが「死の手触り」を感じた様子が伺えました。

棺桶から出たら、一カ月後の自分に向けて手紙を書きます。「死」を意識した直後とあって、どの方も真剣な面持ちで便せんに筆を走らせていました。
トークセッション「主文、終わりのはじめかた」

なぜ私たちは「終わり」をネガティブなものとして恐れ、目を背けているのか。人口低減社会に突入し、世界に先んじて多くの「終わり」を迎える日本において、社会も個人も、避けられない「死」や「終わり」とどうやって向き合い、受け入れていくべきか。
本イベントの共創パートナーである株式会社むじょう代表取締役の前田 陽汰さんと、佛現寺 副住職の油小路 和貴さんをゲストに迎え、モデレーターのTBWA\HAKUHODOの田貝 雅和さんと「終わりのはじめかた」について語り合いました。
──日本は世界に先んじて終わりの時代を迎えることになる
前田:株式会社むじょうの前田です。「諸行無常」からとって「むじょう」という屋号です。主に葬祭関連の事業を軸にしつつ、終わりゆく物事をどう閉じていくのかというところを専門にしている会社です。当社のビジョンは「変化にもっと優しく」です。人の死だけじゃなく、ビジネスに関しても適切な畳み方、終わらせ方を探っています。
田貝:このビジョンが生まれた背景には前田さんの高校時代の経験があると伺っています。
前田:私は高校時代、島根県の隠岐島にある海士町の高校に留学していました。海士町って地方創生の文脈で有名な自治体なんですけど、それでも集落単位だと10年後の存続が危ぶまれる地区もあります。地域活性化こそが正義という風潮のままだと、住人たちは自分の代でたたんでしまう罪悪感、後ろめたさを抱えながら亡くなっていくことになる。そのような成り行き任せの未来を見据えた時に、終わりや変化に対して優しいまなざしを向けられる風土ってどうやって作るのかについて考えるようになりました。
 「拝啓、柩の中から展」の来場者と談笑する前田さん(中央)
「拝啓、柩の中から展」の来場者と談笑する前田さん(中央)
前田:そのヒントは「死」という終わりの体験です。「野垂れ死ぬ」という言葉があったくらい日常に「死」があった社会から、医療が発展し、公衆衛生が充実し、病院で死ぬようになり、死と出会う機会がなくなっていった。それゆえに死に対する免疫がなくなっていった。そこで、現代にあった死との出会い方を考えることが死の免疫、つまり終わりに対する優しい眼差しを向けるメンタリティを育てていくんじゃないかと考えて、死との出会い方をリデザインする事業を通じて死の手触りを感じてもらおうと思っています。
油小路:佛現寺、副住職の油小路 和貴と申します。お寺って本来は文化や教育の発信地、いわばコミュニティのハブとして機能していた場所ですので、お寺を人生のとまり木のような存在にしたいと活動しております。その中のひとつが、「てらのみ」という活動です。名前の通り、お寺で日本酒を飲む会です。合間に簡単なお勤めと、あとお説法とまではいきませんけども、ちょっとお話をさせていただいてる次第です。
 油小路さんと「てらのみ」の様子
油小路さんと「てらのみ」の様子
油小路:無常というのは、全てのものは常に移ろい変わりゆく、永遠不変のものなどないという仏教の考え方です。「てらのみ」で出す生酒はまだ酵母が生きているお酒で、それを開栓した瞬間から味わいがどんどん変わっていく。その様ってまさに無常であるなと。同じく自分自身もそういった無常な移り変わる存在です。無常な日本酒を片手に、自らも無常な存在であるということを味わっていただけたらと思って開催しております。
田貝:TBWA\HAKUHODOの田貝です。当社が行っているグローバルカルチャーのトレンド調査の中で興味深いものがあります。「Demise Duality」、「終わりの多様性」と訳しているんですが、終わりについてのトレンドがここ最近世界で現れています。 今、地球上での人類の支配が終焉に迫っていて人類はそれを受け入れるべきだという考え方が出てきていて、海外では終末論に関する本が結構売れているんです。

田貝:一方、日本は世界の中でも少子高齢化が進んで人口低減社会に突入しています。2024年の有識者会議では、2100年には日本の人口は半減して、4割の自治体は消滅する可能性があると提言がありました。ただ、世界の人口も2100年頃から右肩下がりで減少に転じるという予測があります。つまり世界が2100年以降に迎える終わりの時代を、日本が先んじて迎えることになる。そんなときに、1000年以上続き、終わりとはじまりを繰り返してきた京都というまちで皆さんと終わりについて考えることは非常に意味があるんじゃないかと思っています。
──「死の免疫不足」日常にあった死が遠ざかっている

田貝:スタートアップとか連続企業とか、新しい物事を立ち上げることを賞賛する言葉は多くある一方で、終わりについてポジティブなムードのキーワードってあんまりない。すなわち始めることは礼賛されるけれども、終わることからは目を背ける空気感があるように思っております。これって一体なぜなんでしょうか。
油小路:まず一宗教者として思うのは、日本人の宗教性があると思います。「死」イコール「ケガレ(気枯れ・穢れ)」というイメージが日本人の中にはすごく残っている。それは仏教が入る前からある考えで、死というものに対してそもそもネガティブなイメージを持っていたと思います。この考えは歴史的にもずっと続いてきているものだと思いますね。
田貝:時代の変遷とともに人の死と生活者との距離感はどういうふうに変わってきたのでしょうか。
「仏教が終わりある命をどう生きるか語らなくなっている」(油小路)
油小路:「葬式仏教」という言葉がありますよね。本来仏教って今を生きる私たちに終わりある命をどう生きていくかを説いていたはずなのに、葬式や法事ばっかりしていて、私たちが生きている間に伝えられることが少なくなっていって、死の悲しみの部分が大きくなってしまったんじゃないかなと思っています。
田貝:死や終わりがネガティブなものであるということは昔から変わらないけれども、死が日常的に触れるものから、起こった瞬間にしか出会わなくなったことによって、死との距離感がさらに遠ざかっていったんですね。実際に葬儀の事業もされている前田さんは、終わりと生活者との距離感について何か思うところはありますか。
「今の社会は終わらせることができないシステムになっている」(前田)
前田:葬儀屋の目線では「死の免疫不足」。冒頭で申し上げたように日常にあったはずの死が遠ざかっていて、それゆえに実感、手触り感がなくて、怖くて拒否してしまう。そういう反応はあるような気がしますね。あとシステムの部分からもお話できるかと思います。例えば、今世界でいちばん時価総額が高い会社が会社を終わらせることって難しい。今日株を買ってくれた人に対してリターンを出すことが株式会社という仕組みである以上、続けることがミッションになってしまう。これってシステム上の問題です。続けることが前提のシステムってビジネス以外にもたくさんあります。プロ野球選手もそうですよね。高い年俸で契約した以上、プレーし続けなければいけない。
田貝:確かに今の資本主義的な世の中だと、 お寺に行って終わりについて考える暇があったらどんどん仕事しろと言われるのが容易に想像できます。なぜ終わりがネガティブなものになったのかというと、世の中のシステムもそうですし、私たちの日常の中からお寺のような終わりについて考える場がどんどん少なくなっていったというのも理由のひとつとして言えそうですね。
──終わりを受け入れたら、自分の基準で生きる人たちが増えていく

田貝:今お二人にお話いただいたように、終わりは目を背けたくなるようなものですが、一方で終わりを気にする兆しが世の中に出てきています。何事も終わりがあるという前提を受け入れた上で、終わった後の自分たちのあり方を探す人が増えてるんじゃないかなと私は受け取っています。
油小路:私はお坊さんになる前に祖母の死に直面して、そこで初めて自分も死ぬんだっていうことを突きつけられました。 そこをきっかけに仏教を学び、無常は当たり前である、という世界のあり方をだんだん受け入れていくことができました。日々の生活を重ねながら、自分も社会も、無常、つまり移り変わり続けていく。私自身、今はそれをちょっとずつ解釈しているところです。
田貝:変化という点では、油小路さん自身が、例えばお寺のありかたが変わる中でどういうふうに受け継いでいくのか、そのあたりはどうお考えですか。
「形はなくなっても、思いの部分は受け継いでいける」(油小路)
油小路:私がお寺での活動を通して真のところで届けたいものは自由です。つまり、自らを指針として生きるという自由を届けたい。だから私はお寺を続けないといけないっていう考えは別になくて、 私の息子にも自由に生きてほしいと思ってるんですね。 私の背中を見てお寺を継ぎたいといってくれたら嬉しいですが、継がなくても構わない。お寺という箱であったり、形のあるものは受け継いでいけなくとも、私の思いのようなものを受け取って、続けていってくれると思います。
田貝:いわゆるお寺という形式を持っていなくても、 油小路さんが受け継いだ仏教的な価値観、その思いの部分が受け継がれていくっていうことの方が大事ということなんですね。
油小路:そうですね。仏教も2500年前のお釈迦さんの時代と比べると形が変わっていますが、思いの部分はブレずに伝えられ続けてきている。灯を受け継ぎ続けたからこそ形が変わっても今のようなお寺の文化になっているのだと思います。
田貝:ハードではなくてソフトの部分で受け継いでいく、例えばお寺がなくなるという形で終わりがきても、思いは受け継がれて終わりがないと思えるかどうか、でしょうか。今の話を前田さんはどう思われましたか。
「これまで広げてきたものを適正な規模にたたむことは悪いことじゃない」(前田)
前田:ハードに関してはそんなに問題にならないと思っています。血縁の外にいる方がお寺をやりたいといって佛現寺さんの箱を使うのもひとつですし、お寺自体はたたむこともできるわけです。これまで広げてきたものを適正な規模にたたんでいく作業はそんなにネガティブなことではないという印象を受けました。
田貝:どちらかというと、ハードに込めた思いの部分がどう受け継がれていくかっていうことを考える方が大事だと。
前田:そうですね。価値観はどんどん変わっていくものです。いい学校に進学して、いい会社に就職して、たくさんお給料をもらって、というこれまでの成功のステレオタイプが、成長し続ける時代がもうすでに終わりつつある中で「そんなに稼いでるわけじゃないけれども楽しそうに生きている人」に変わりつつある。いまインフルエンサーが人気を集めている理由は、お金だけが価値判断の基準じゃなくなって、面白いことをして生きている人への憧れが強くなってきているから。終わりを受け入れると、判断軸がどんどん変わっていくんじゃないか。それはすでに起きているんじゃないかという気はしますね。

田貝:終わりを受け入れた先にある日常っていうのは自分の基準で生きている人たちが増えていくような世界なんでしょうか。
油小路:自分にフォーカスしていくという流れは仏教と近しいところがあります。仏教ってすごく個人的な宗教でもあるんですね。自らが仏になるための道、仏道は、宗派によってアプローチが違いますが念仏や座禅をすることによってとにかく自分を掘っていく。すると今この私を構成しているこの肉体も、いろんなこの思想も、生まれてから変わっていないものはひとつもない、いろんなご縁をいただいて、影響されている。自分を問えば問うほど、他者とのつながりやご縁が浮き彫りになっていく。 個人主義になりつつも他者とのつながりが感じられる、そういった社会や日常に変わっていったらいいなと僧侶としては思います。
田貝:自分の好きなこと、自らの指針というものを突き詰めていくことによって、 ある意味で周りの縁に支えられてるっていうことに気づくことがある、と。 それって面白いですね。

前田:今の話ってSNSでも起きていると思います。たとえばyoutubeって個人が目立っていくツールでした。次にInstagramはハッシュタグで繋がるっていうところが盛り上がった。ひとりじゃ楽しくない、それだけだと満たされないものがあるからこそ、共通の関心で繋がることにユーザーが流れていった。
田貝:自分の好きを突き詰めていくだけだと虚しくなって、ハッシュタグでの繋がりに移っていくところは、仏教的な変化をたどっていると言えそうですね。
前田:その次に出てくるTikTokがまた面白くて、ご縁的な発想が出てくるんですよ。TikTokのアルゴリズムで、フォローしていない人の動画も出てくるんです。人がたくさんリアクション、アテンションをして評価されたものがおすすめされる。共通の関心という関係で繋がっていたInstagramから、TikTokは偶発的な出会いに移行していった。SNSは本当に世相を反映している感覚がありますよね。
「徹底的に自分と向き合うことを世の中が求めはじめている」(田貝)
田貝:アルゴリズムで「あなたが好きなものはこれなんでしょ」って提案されたものって自分の外側にあるシステム、つまりハードに提案されたものですよね。最近は、自分と向き合う瞑想系のアプリが出てきているんですよ。今度は自分の外側に基準を持つんじゃなくて、徹底的に自分の「好き」と向き合うことを世の中が求めはじめている。確かに世相がぐるぐる回っているなっていう感じがしますね。
──終わりを受け入れるためには、その解像度を上げていくことが必要
田貝:次にお話ししていきたいのが、終わりゆく世の中を受け入れた上で、どういうふうに意志ある未来へ持っていったらいいのかということについて考えていきます。今回、こちらのトークセッションと合わせて、同時開催していたのが、むじょうさんと一緒にやらせていただいた「拝啓。棺の中から展」です。終わりの受け入れ方を 体験する機会としてこの展示を実施しました。
前田:私たちが必要だと思っていることが「解像度を上げること」。例えば病院で具合が悪くなって看取る直前になると、病院の先生から「人が亡くなるとき、最後は苦しそうな呼吸になります」という説明があります。下顎呼吸というんですけど、それを知らないと「苦しそうだな、大丈夫かな」と焦りますよね。でも事前に知っていると「先生が言っていたことだな」って落ち着いて看取ることができると思うんです。

前田:解像度が上がった状態であれば、ゆっくり考えることができると思うんですよね。そこで、自分の死というものに対する解像度を上げる営みとして、棺の中に入っていただいて、1カ月後の自分に宛てた手紙を書くという手を動かす体験をしていただきました。
油小路:この日の夜、お堂の真ん中にこの棺を置いて、その周りを囲んで日本酒を片手に無常について語り合ったんですけど、こういう死に対するフランクな携わり方が必要だと思っています。というのも、自分の死という縁起でもないことを、 行政でも民間でもない、お寺っていうちょっと不思議な場所ならなぜか話せる。その空気感の中でいろんなご縁をつなぐことってすごく素敵です。

油小路:私、前田さんの言葉ですごく好きなのが「死の手触り感」なんですけど、その言葉のように、死を前向きに受け入れる場所になっていて、私自身もお酒を注ぎながら楽しませていただきました。
田貝:お二人の事業の共通点として、前田さんの場合だと実際に棺桶に触って入ってみる、 油小路さんの場合だと日本酒を飲んでみるっていうように、頭で考える機会を作るというよりは五感や自分自身の感性で「終わる」って一体何なのか、肌触りを提供していますよね。
「終わりを受け入れるには、無常観をインストールする」(前田)
前田:自身の死に対する解像度を上げることのほか、終わりに対する捉え方を変えることですね。たとえば消滅可能性自治体の話だと、人口が0になることイコール消滅と定義をすると、確かに消滅する可能性はあるかもしれないけれども、ただ人が住まなくなるだけで動物のパラダイスになるかもしれないし、土地は終わらない。でも、今は人が住まなくなっただけ、という捉え方ができてない。 それはもうしょうがない、というメンタリティを、私たちは「無常観のインストール」という言葉を使っているんですけど、そういう無常観をインストールする機会をどんどん作っていくことが、終わりの新しい受け入れ方になっていくんじゃないかなと思っています。
「生き続けることは死に続けること。終わりの手触りを伝えたい」(油小路)
油小路:仏教に「生死一如」という言葉があります。今の私たちには、生きることがスタートで死ぬことがゴールのようなイメージがあると思うんですけど、仏教では生き続けるということは死に歩みを進めること、生き続けながら死に続けているという考え方があります。例えば、私たちって花が咲いて散っていく様に死を感じるけども、花が散った後に種ができて、その種が地面に落ちて、 また芽吹いていくとき、それはひとつの終わりではあるけども、また始まりにもなる。田貝さんがおっしゃったように、その手触りを説法で伝えていけたらなと思っています。終わりは始まりでもあるし、始まりにするかどうかは自分のその受け止め方次第です。真正面からありのままに受け止めるっていう、新しい受け入れ方ができたらなと思ってます。
田貝:先ほど、自由という自らの指針で物事を考えていくというお話がありましたけど、さっきのSNSの話のように「あなたはこれが好きでしょ」って提案される世の中で、自分の自由を突き詰めていくのって、実は結構難しい世の中な気がしています。どうやったらそこにたどり着くことができるんでしょうか。
前田:それって、自由を突き詰めてるわけではないのかもしれません。油小路さんに限らず仏教の根本にあるものって囚われないことを目指す教えだと思うんですよね。 いかに自然体で囚われない状態を歩んでいくのか。多分、自分の仏道を歩むというのは、その教えを守るということなんじゃないかなって、お話を伺いながら思いましたね。
油小路:本来仏道ってめちゃくちゃ苦しいことなんです。嫌なところもある自分っていう存在にありのままぶつかっていかないといけないところが仏道の苦しいところではあるけども、 自分が納得して終わりを求めるのであれば必要な過程。終わりに対する手触りとか、終わりが始まりでもあるということも、知っているだけじゃなくて分かっていく。それが終わりを受け入れた社会の先の姿でもあるのかなって、今なんとなく思っています。
「続けることにも終わりにも囚われない。今の積み重ねが死という最後の締め切り」(前田)
前田:今のお話を聞いていて、終わりを受け入れるというのも傲慢な表現だという気もしてきました。受け入れることの前提には、囚われないということがある。続けることにも囚われないし、終わりにも囚われない。今を生き切って、今の積み重ねが死という最後の締め切りだと思った次第ですね。

田貝:確かに、続けることにとらわれない人は油小路さんのように今を生きている人で、今を生き切るためには、自分の周りにあるハッシュタグや一般論ではなくて、自分自身の内にある感覚に素直になる必要がある。五感に訴えかけるような体験をお二人が提供していることと繋がるように思います。
「今を続けなきゃいけないという感覚に囚われることなく、今の自分を楽しむ」(田貝)
田貝:死に代表される「終わり」は偶発的なもので、自分の意志の及ばない外側からきっかけがやってきて終わってしまう。その外からやってくる「終わり」に対して、特に今の世の中は考える機会が希薄になっていて、ネガティブに受け止める既成概念がある。ですが、自分の内側、言い換えると意志の部分では終わりというものはなく、続いていくと思えるかどうかが大事で、そこに望ましい未来があるのかなと思いました。 自分自身が今っていうものを続けなきゃいけないという感覚に囚われることなく、今の自分に向き合い、今の自分を楽しむことが、終わりを受け入れる上で大事になると思います。
「コントロールできないものを受け入れる寛容さが、しょうがないというメンタリティ」(前田)
前田:「しょうがない」というメンタリティが持ちづらい世の中になっていることが、もしかすると冒頭で話した「なぜ終わりにはネガティブなイメージがあるのか」という問いに対する答えかもしれません。隠岐島では漁師さんがよく「しょうがない」って言うんですよ。今日は海がしけているから船を出せない、しょうがない、と。自然の方が主導権を握っていて、人間はその中で生かしていただいてる存在なんだっていうのが自然とインストールされているんですよ。その感覚があれば、町の終わりに対しても「しょうがないよね、人が減っているし」と言える。人間がコントロールできると錯覚すると終わりが苦しくなる。死もまたそうで、しょうがないと受け入れられる寛容さや捉え方にもヒントがありそうだなと思いました。
「諦めるとは、ありのままに見て受け入れること」(油小路)
油小路:「しょうがない」って仏教チックで面白いですね。仏教に「四諦八正道」という言葉がありまして、本当に簡単に言うと四つの真理とそれに対する八つの実践方法という意味なんですが、「諦める」って漢字を見るとなんだかネガティブな感じがしますよね。でもこれは「あからめる」、明らかにするという言葉が語源になってるんです。外部からやってくるものを「あからめる」、諦める気持ちを持ってありのままに見て、受け入れ方も考える。「しょうがない」と諦める心を持つことが新しいあり方になっていく。今はそこが否定的に捉えられてるけども、いや違うんだよ、と。個人も社会も今の時代に合わせてありのままに「諦めていく」こともひとつのあり方かもしれません。
田貝:お二人とも、ありがとうございました。終わらざるを得ない状況に対してなんとか続けていくことが今の既成概念だとしたら、しょうがないと受け入れていく心の持ちようがこれから先は大事になっていくということでしょうね
(写真:QUESTION 石津亮)
ARTICLES