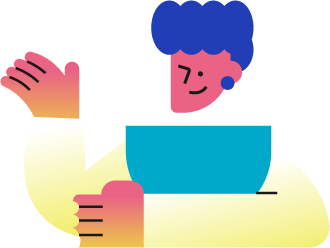「With QUESTION」5周年 特別対談01
問い続けた5年と、その先の未来へ。
QUESTIONの今までとこれから

QUESTIONは金融機関の建物。しかし、1階にはカフェ&バーが広がっていて、コミュニティ・バンク京信の店舗は1階ではなく6階にあり……、「ここは何をしている場所なの?」と疑問を抱く人も少なくありません。
連載「With QUESTION」では、オープンから5周年を迎える今、改めて「QUESTIONとは何か?」を、これまで関わってきた皆さんと共に考えたいと思います。この5年でさまざまなイベントが開かれ、たくさんの人々が言葉を交わし合った大階段「Community Steps」に腰かけて、QUESTIONの過去・現在・未来について語り合いました。
お話を伺った人
-
榊田 隆之コミュニティ・バンク京信 理事長
上智大学外国語学部を卒業。1985年に京都信用金庫入社、2018年に理事長就任。徹底的な対話型経営により「日本一コミュニケーションが豊かな会社」を目指す。1971年に「コミュニティ・バンク」を世に提唱した金融機関の理事長として、地域の経済や文化の形成への想いを込める。
-
󠄀󠄀平野 哲広QUESTION 館長
大阪生まれ、京都育ち。2001年京都信用金庫に入庫。営業店と本部を経験し、2024年4月にQUESTION館長に就任。コミュニティマネージャーとして金融の枠を飛び越え、様々な人や知識、知恵、情報と繋がり、人と人、事業と事業をつないでいる。伏見のお酒が好き。趣味はサッカー観戦とギターを演奏すること。
コミュニティ・バンク京信が表現する、これからの金融機関の姿
平野 2024年からQUESTIONの館長を務めていますが、利用者の方に「なぜ金融機関のコミュニティ・バンク京信(以下、京信)がQUESTIONをつくったのか」とよく聞かれます。改めて、なぜQUESTIONをつくったのか教えてください。
榊󠄀田 我々のような信用金庫は、地域を元気にしていく存在であるべきです。お金を融通するだけではなくて、コミュニティをつなぐ役割も担う必要がある。この河原町ビルを建て替える際に、「21世紀の金融機関の姿」を表現したいと思ってつくったのが、QUESTIONでした。
5年間やってみて分かったのは、コミュニティは計画的につくるものではなく、人の心が動いたときに偶発的に広がるものだということでした。心でつながるコミュニティが地域を豊かにしていく……そんな動きが日本全体に広がっていくことを思い描きながら、さまざまな取組を行っています。

平野 京信が50年以上前から行動理念として掲げてきた「コミュニティ・バンク論」に通じますね。
󠄀榊󠄀田 そうですね。結果的にQUESTIONができたおかげで、「コミュニティ・バンク京信」を目指すという方向性が確信に変わったように思います。この共創スペースが社内・社外の双方に変化をもたらしていることを、今まさに実感しています。
平野 もうひとつ、よく聞かれる質問が「なぜさまざまな施設を入れているのか、その発想はどこから来たのか」。そのあたりはいかがですか?
󠄀榊󠄀田 発想の起点は「人と人との交流」にあります。バンキングフロアを1階から6階に移して、1階をカフェ&バーにしたのはそのためで、雑談やお茶を通じて自然につながれる“ゲートウェイ”にしたかったんです。
2・3階のコワーキングスペース、3階から4階にまたがるCommunity Steps(イベントスペース)、5階のStudents Lab(学生が無料で使えるオープンスペース)、8階のDAIDOKORO(コミュニティキッチン)など各フロアで役割は異なりますが、人と人とがリラックスした状態で交流できる場、というコンセプトは共通しています。
特にDAIDOKOROでは、料理を一緒につくることで、理屈や肩書きを超えた関係が生まれていると感じます。「この人となら一緒にやりたい」と思える関係ができていくのは、まさにコミュニティ・バンクが目指すところです。
平野 QUESTIONの設備を実際に使ってみると、本当にいいアイデアが詰まっているなと感じます。5階のStudents Labも特徴的ですよね。ワンフロアを学生に開放しようと思ったのはなぜですか?
󠄀榊󠄀田 未来を担う若い世代に、多様な体験をしてほしいと考えたからです。社会人が一方的に支援するのではなく、共に活動することに意味があります。最近では、当初想定していた大学生だけでなく、高校生や中学生、小学生にも関わりが広がっています。
平野 若い人たちはこれから未来をつくっていく立場でもありますし、何より柔軟な発想には大きな力がありますよね。私たち社会人が学生の皆さんから学ぶことも多いなと思います。

5年はまだ途中経過。10年、20年かけて地域の風土として根付いていく
平野 開設から5年、当初の未来像には近付いていますか?
榊󠄀田 明確な未来像は持っていませんでしたが、人と人との関係性を整えることが重要だとは感じていました。私が考える理想的な社会というのは、一人ひとりが自分を主語にして、地域のことを語れる社会です。自分の考え方やスタイルを持って、自分ごととして考える。それがコミュニティの形成において大切です。
コミュニティでは仲良くするだけでなく、時にぶつかり合いながら相互理解を深めていく必要があります。AIには解析できない、人にしかできない複雑で深い関係性の中で未来をつくっていくこと。これが私たちの目指すべき世界なのかなと思います。今、QUESTIONではその世界観を多くの方々と共有できているように感じます。
立ち上げ当初は迷走しましたが、同時多発的にプロジェクトが芽生えて広がるようになり、進化を実感しています。今後はさらにプロジェクトの精度を上げつつ、地域の中で「QUESTIONのコミュニティは心地いい」と体感していただけるような取り組みを、焦らず急がず広げていきたいですね。こうした取り組みは10年、20年かけて地域の風土として根付いていくものだと考えていますから、そういった意味では5年というのはまだまだ途中経過かなと。
平野 では反対に、この5年で予想と違った点はありますか?
榊󠄀田 当初は「課題解決の場」がたくさん生まれると想定していましたが、実際は「雰囲気が好き」「人と親しくなれる」といった和やかな場としての側面が強まりました。その雰囲気が「生ぬるい」と思われることもあります。しかし、QUESTIONは短期的な成果よりも、中長期的なコミュニティ育成を目指す場です。その意味や価値を地域に丁寧に伝える必要性を感じています。
とはいえ、まずは自分たちが楽しむことが一番。カフェやキッチンで料理を囲み、会話を楽しむ、そんなQUESTIONらしさは忘れずにいたいですね。

平野 これまでの5年間で「QUESTIONの未来につながる」と感じたエピソードはありますか?
榊󠄀田 たくさんありますよ。具体的なエピソードを挙げるなら、Students Labに来ていた宮武愛海さんがアクセサリーブランド「sampai」を立ち上げたことが印象的でしたね。最初は一人でポツンと座っていた彼女が、コミュニティマネージャーに声をかけられて心を開き、仲間と共にブランドを立ち上げた。思いと情熱が共感を呼び、仲間が支える、というQUESTIONのあるべき姿を見たように思います。
京都市と連携して、京都市役所前広場を市民に開かれた場所にすることを目指して定期的に行っている「小さな芝生広場の実験」プロジェクトも、まちの人たちが主体的にまちのことを考える場として意義があり、大きな可能性を秘めていると感じます。「QUESTIONタウンミーティング」も開催され、市民の皆さんと京都市長と一緒になってまちの未来を考えることができたのは、とても良かったと感じます。
金融機関と行政との連携というとただ協定を結んで終わってしまうケースも多い中で、QUESTIONは京都市役所の向かいにあって距離が近いからこそ、自然発生的にさまざまな連携が生まれています。今後もこのQUESTIONという場所が、京都の未来を考える場として活用されていってほしいですね。

平野 どちらもQUESTIONと地域の未来の広がりを感じるエピソードですよね。私は「京都はたらく交流会」が印象に残っています。中小企業や大手企業の支社の新入社員には同期が少ないという背景をもとに、まち全体を1つの会社と見立てて、相談できる仲間をつくる仕組みとして始めた交流会で、不定期に開催しています。
ただ仲良くなるだけではなく、10年後、20年後に役職についたとき「若い頃から知っているあの人なら信頼できる」と、すぐに協働できる関係性をつくりたい。この発想は、営業店や本部では考えつかなかったかもしれません。QUESTIONだからこそ、自由な発想で実現できたのかなと思っています。
理想は「日本国民全員コミュニティマネージャー」
平野 榊󠄀田さんは以前、アメリカのポートランドを視察されてその風土に共感した、というお話をされていましたよね。
榊󠄀田 10年ほど前の話になりますが、当時アメリカで最も住みたい街と言われたポートランドを視察し、多様性や共創を重んじる価値観にあふれるまちづくりに共感を覚えました。その魅力の源は、建物や道路といった立派な設備ではなく、人と人との雰囲気や空気感にありました。
心と心のつながりがまちを豊かにする。魅力的な場所とは、やはり人間関係のような目に見えないものを大切にする、人情味ある場所なのだと思います。そのスタイルは今のQUESTIONにも息づいています。
平野 そういった人間関係をつくっていく中で、󠄀榊󠄀田さんは「緩やかなネットワーク」という言葉をよく使われている印象です。
榊󠄀田 普段はつながっていなくても、いざというときには連絡を取り合って一緒に何か動けるような、つながったり離れたりしつつも、心はつながっている関係性のことをそう表現しています。そこにデジタルの力が加われば強力です。QUESTIONの根底にもその発想があります。
京信ではこの5年間、働き方のあるべき姿をみんなで一緒に考えてきました。例えば副業制度を導入したこともその1つ。今では多くの職員が副業に挑戦していますが、導入当初は「本当に大丈夫?」と不安がありました。
そういった不安を「やっていい」と確信に変えるには、コミュニティを通じて刺激を受けることです。先駆者や自分とは違う世界の人が近くにいると、価値観の広がりも加速していきます。緩やかなネットワークの中でそういったつながりが生まれていけば、人の価値観を広げて充実させていくことにつながるのではないかと思います。

平野 QUESTIONは、まさにそういった「他流試合」ができる場所ですよね。人との出会いが、自分の中にあるモヤモヤへの答えになることもあると思います。ただ、出会いを結びつけるコミュニティマネージャーの役割も大きいですよね。
榊󠄀田 そうですね。理想は誰もが自然につながれる、いわば「日本国民全員コミュニティマネージャー」な社会ができたらいいなと。でも、現実には間をつないでいく“おせっかい役”が必要です。だからこそ、QUESTIONのコミュニティマネージャーには「この人に相談したい」と思われる存在であってほしいですね。
広がる“QUESTION化”の輪が大きなエネルギーに
平野 社内全体を見て、コミュニティ・バンクとしてのあり方は広がっていると感じますか?
榊󠄀田 そうですね。コミュニティ・バンク京信が全国の金融機関に先駆けて挑戦している「課題解決型店舗」では、窓口営業を午前9時から正午までとし、午後はお客様の事業や暮らしのご相談、地域社会の課題解決などに取り組んでいます。2024年6月から順次導入店舗を増やし、各支店がより一層地域と共に動ける仕組みへと変革を進めています。
そうした流れの中で、全店で「QUESTIONを目指そう」という感覚が広がっており、95店舗それぞれがQUESTION化に取り組み始めています。精度はまだそれほど高くはありませんが、地域の中でお客様を知り、つなぎ、寄り添う動きが各店舗に根付きつつあります。QUESTIONだけでなく「コミュニティ・バンク京信」としての進化も、この5年で相当大きなエネルギーになってきていると感じます。

平野 振り返ってみると、本当に変化の大きい5年間でしたよね。特にコロナを経て、人々の価値観も大きく動いたと思います。その中で京信は地域のお客様と向き合い、課題を解決しようと努力してきました。一人ひとりが自分ごととして地域やお客様のことを考え、行動してきた結果、スキルだけでなく気持ちの部分でも、京信の職員全体が大きく成長したのではないかと感じます。
榊󠄀田 この5年間で、みんな腹落ちしてくれたんじゃないですかね。以前は理想論に聞こえていたことが、自分ごととして確信に変わってきた。これは大きな進歩です。

平野 私はQUESTIONに来てから、京信のエリア内どころか、全国から来られるさまざまな人と出会えるようになりました。たくさんの方と出会うことで、金融機関の枠を超えて20年後、30年後を一緒に考えられるようになったのは、私にとって大きな変化でした。
営業店にいた時は、「結果が伴うかどうかわからないことを、なんで今せなあかんのやろ?」と思ったこともありました。でも、QUESTIONに来て考えが変わりました。これからQUESTIONのような動きをする課題解決型店舗が増えていけば、そこでも同じように、自分たちのいる地域の未来を積極的に考えられるようになるのではないかと思います。
榊󠄀田 焦らず自然体で続けていけば、みんないつか腑に落ちる瞬間が来ると思うんです。実際、この5年で多くの人が変化を実感できるようになってきました。今後も一人ひとりが「自分ごと」として行動できる場にしていきたいです。
やっぱりコロナ前とアフターコロナの今とでは、働き方や人々の感覚など、いろんなものが変わったなと思います。QUESTIONがこの5年間を歩んできたことは、これからの京信の歴史にも残っていくのではないでしょうか。
梅小路・京都駅前にも広がるQUESTIONのネットワーク
平野 私はこれまで、京信で営業店や人事部など幅広く経験してきましたが、QUESTIONに来て「自分は狭い世界にいた」と痛感しました。ここでは多様な人が集まり、驚きや学びが絶えません。だからこそ、まずは社内の人たちにもっとこの価値を感じてもらいたいなと思います。そうして社内で価値をさらに理解してもらえたら、地域の方々にも自然と価値や意義が広がっていくはずです。

榊󠄀田 そうですね。今後のQUESTIONに必要なのは「自分が関わったからこそ、このプロジェクトが実現できた」と語れる人を増やすこと。QUESTIONや京信を主語にするのではなく、自分の言葉で地域を語れる人だらけになっていってほしい。人が自己成長するには、そうして自分ごととして何かに取り組む経験が必要です。それが地域社会やコミュニティ・バンクを支える人づくりにもつながるんです。
「Umekoji MArKEt」にも「QUESTION梅小路」があり、今後は大阪ガス都市開発・龍谷大学と共同でつくるイノベーションハブ拠点「共創HUB京都」にも「QUESTION京都駅前」を設置予定で、他の場所にも広がっていくかもしれません。これからはQUESTION同士がつながり合い、それぞれの得意分野やスタイルを活かしながら有機的に協働していくことも大切です。
お互いに自立しつつも、違うもの同士が結びつけばより大きな力となり、社会を変える原動力にもなります。多層的、複層的なコミュニティのつながりを育てることが、我々QUESTIONの社会的役割なのではないでしょうか。
平野 ネットワークが広がるほど、問いに対する答えを持つ人も増えていくはず。QUESTIONは、いかにそのハブとなって情報をつないでいけるか、というところが重要になってきますね。
QUESTIONにとって、この5年はまだまだ道半ば。開設当時から変わらず大切にしてきたコンセプトを守りつつ、楽しみながら、ワクワクしながらまた次のステップに進んでいけたらいいのかなと思います。

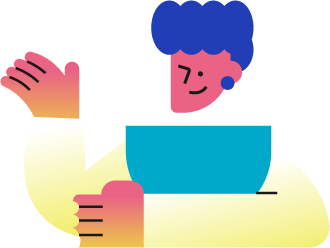
ARTICLES