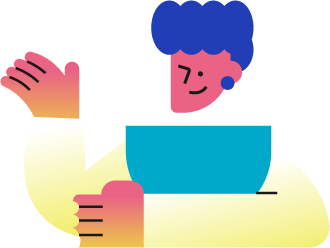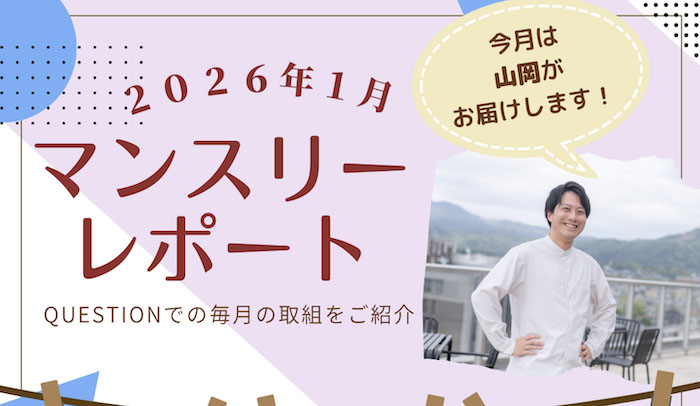ARTICLES
記事
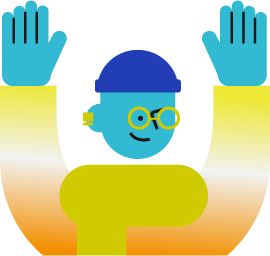
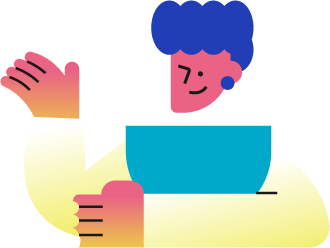

今回お話を伺ったのは、宇治市で「シェア型書店HONBAKO京都宇治」の運営をスタートした山本 奈々さんと、宇治市役所産業振興課の小松原 紀一郎さんです。
シェア型書店とは、店内の「本箱」を利用者がレンタルし、「箱主」として自分の本やおすすめの本を販売できる新しいスタイルの書店です。山本さんは京都府宇治市に移住し、地域の市民活動に積極的に参加する中で「シェア型書店を宇治に開きたい」という思いで各地を奔走。2025年3月、大阪府堺市の「makoroplanHONBAKO」の、のれんわけとして「シェア型書店HONBAKO京都宇治」をオープンしました。
今回は、QUESTIONコミュニティマネージャーの石津 亮が、山本さんと、山本さんのチャレンジを支えてきた宇治市役所産業振興課の小松原さん、コミュニティ・バンク京信 宇治支店の望月 菜央子さんに、オープンまでの背景や想いを伺いました。
お話を伺った方
- 山本 奈々さん
幼少期に日本昔話や偉人伝、学生時代に女性作家のエッセイ、小説に親しんだこと、また、子育ての中で関わった絵本の読み聞かせのボランティア活動をきっかけに本や読書家の魅力に目覚める。IT企業、ウェディング、カフェ、銀行、行政書士事務所、Web広告、食育など多様な業種を経験し、現在は宇治に暮らし、地域コミュニティや食育活動、シェア型書店HONBAKOなどに関わりながら、「本を読む人が好き」「読書家の集まる場所は地域の資産になる」という思いを軸に活動している。 - 小松原 紀一郎さん
2014年入庁。政策部局を経て、2022年より産業支援に従事。派遣研修の名目で京都府の外郭団体にて多くの企業訪問を経験し、府内ものづくり企業の販路開拓支援を行う。2024年より現在の所属に帰任してからは、創業補助金、若者向けの創業機運醸成事業「宇治市こども未来キャンパス」や就労支援事業など幅広い形で産業支援に携わる。 - コミュニティ・バンク京信 宇治支店 望月 菜央子さん、QUESTION コミュニティマネージャー 石津 亮
誰かとつながりたくて、積極的に宇治のコミュニティに飛び込んだ
石津:奈々さんが宇治に移住したのは今から2年前ですが、宇治のまちづくり活動に参加されるようになったきっかけは何だったんでしょうか。

山本:宇治に移住したものの、知り合いや友達が全然いなかったので、誰かとつながりたい、宇治のことが知りたいと思って「うじらぼ(※)」に出入りするようになりました。うじらぼに行ったら誰かしら面白い人がいるし、宇治のことでわからないことを教えてくれる人がたくさんいたので、その中で自然と関わる人が増えていき、まちづくりに関する活動にも呼んでいただいたって感じですかね。
(※)宇治NEXT(宇治市・宇治商工会議所)が運営する、産業振興につながるプロジェクトや事業者の活動など、様々なアイデアを育て、実践するための「産業交流拠点」。コワーキングスペースの機能を有しつつ、市民や団体、事業者、行政が協力しながら、宇治のまちをより良くするための企画を検討し、実施する場として活用されている。
小松原:創業前支援のセミナーや交流会によくご参加いただいていましたね。山本さんもそこで刺激を受けられたというか、いろんな宇治の方に出会って、自分で何かしようというイメージをつけていかれたのかなと我々は捉えています。
山本:うじらぼを利用し始めた当初は、自分が何か事業をすると考えてはいませんでしたが、何か事業を起こすんだったらうじらぼの人たちに相談したらいいんだなっていうのは感じていました。
山本:宇治を知るために宇治NEXTが開講している講座にいろいろと参加してみたり、「京都府女性の船」(※)という京都府の事業にも参加してみたりして、京都ってどんなとこかな、宇治はどんな地域なのかな、どんな人がいるのかなと学んできた感じですね。宇治のお茶摘みの体験や仕事にも参加したんですよ!
(※)京都府が実施している、地域づくり・NPO活動等に関心のある女性や、職場などでさらに能力を発揮したい女性に、学習とネットワーク構築の機会を提供し、地域・職場の課題解決や社会・経済の活性化のために活躍する女性リーダーを育成するための研修。
小松原:そうそう。僕が初めて奈々さんに会ったとき、奈々さんはお茶摘みさんの格好をしていました。

山本:体験の時にお茶摘み娘の衣装を借りることができるんですよ。それを一度着てみたくて、女性の船のOGメンバーと一緒に衣装をまとって、産業振興課に行きました。「見て見て~!」って(笑)
小松原:僕は事務所でポカンとして見ていました(笑)
石津:小松原さんや産業振興課の皆さんには、当金庫もQUESTIONもいつも大変お世話になっています。皆さんは普段QUESTIONと、どんなふうに関わってくださっているんでしょうか。
小松原:QUESTIONで行われている異業種交流会によく参加させてもらっています。そこで出会った方と、一緒に何かしようって意気投合することもありますよ。我々も常日頃から役所の外に出て新たな繋がりを作って、市内の事業者さんに還元したいと思っています。QUESTIONに出かけると我々の視野を広げてくれるので、ありがたいなと思っています。
石津:こちらこそありがとうございます。宇治NEXTの皆さんはQUESTIONや宇治支店に協力的な姿勢でいてくださるので我々も何かと相談しやすいです。 うじらぼの運営母体である「宇治NEXT」では、どんな思いでまちづくりに取り組んでおられるのでしょうか。

小松原:宇治NEXTは令和元年に宇治商工会議所と市役所の産業振興課が一体となって開設しました。それまで分かれていた市内の産業支援の窓口を一本化して事業者の皆さんが相談しやすい体制を整えました。商工会議所さんは経営支援などのノウハウはもちろんのこと、地元の事業者さんとの繋がりが強いですし、我々はそういった部分で商工会議所さんの力を借りながら宇治市産業戦略を策定して、宇治NEXTとして、補助金の運用、創業あるいは創業前支援を企画していくという連携をしています。
石津:産業振興課なのでまちづくりは直接的な業務ではないですよね。どっちかというと産業分野ですよね。
小松原:所管だけの話をするとそうなんですが、手段は違えど、まちづくり、地方創生という目的は一緒なので、常日頃から部局横断的にやっていきたいと思っています。
石津:そして、奈々さんがQUESTIONを知ったのは、うじらぼで僕と知り合って、QUESTIONの交流会に参加してくださったことがきっかけですよね。「シェア型書店をやりたいんです」ってチラシを持ってこられたことを覚えています。
山本:シェア型書店を宇治でやろうと心に決めて店舗物件を探し出していた頃ですね。QUESTONに出入りしながら「物件を探しているから、物件情報があったら教えてください」って伝えに行ったり、「つながるピッチ」に参加させてもらったりしました。
石津: そうそう、QUESTIONの会員交流会「つながるピッチ」や、僕が関わっている方を集めた交流会「わかんNight」でシェア型書店について熱く説明していらっしゃいました。
 異業種交流会「わかんNight」の様子(右から2番目が山本さん)
異業種交流会「わかんNight」の様子(右から2番目が山本さん)山本:そうやって宇治市内のいろんな市民活動、ボランティア、また市外の交流会に参加して人脈を広げながら、一方で物件をずっと探し続けていました。
石津:物件は宇治限定で探しておられたんですか。
山本:はい。やっぱり宇治が良かったんです。うじらぼで素晴らしい才能を持つ方々と出会っていたし、面白い方がいっぱいいることを知ってしまったから、どうしても宇治市内で事業をやりたいと思っていました。
宇治だからこそ実現できたコミュニティビジネス
石津:奈々さんが大阪堺のシェア型書店HONBAKOと出会ったのは、ご自身の食育活動がきっかけですよね。
山本:はい。自分の食関連の活動がちょっとでもPRできたらと思って、箱主のひとりとして堺市のHONBAKOの箱主になり参加したのがきっかけです。店長さんが友人ということもきっかけの一つにありました。そこで本好きの方や箱主さん達の魅力にハマりました。知識や人生経験が豊富なことはもちろん、優しかったり思いやりがあったり、様々な人の立場で物が考えられたり、「本好きさん達ってこんなにも素敵なんだ」って。彼らと関わる中で、地域と関わる活動がHONBAKOの箱主さん達から広がっていくのもずっと見てきたので、自分が移り住んだ宇治にもHONBAKOのようなシェア型書店があれば、きっと何か新しいものが生み出されるんじゃないか、自分が住む町の資産になるんじゃないかと思ったんです。
 山本さんが感銘を受けた、HONBAKO堺の箱主の皆さん。
山本さんが感銘を受けた、HONBAKO堺の箱主の皆さん。山本:「HONBAKOを京都にも作ってくださいよ」って、実は堺のHONBAKOさんにずっと言ってました。HONBAKOみたいに本で繋がれる読書家たちの居場所があったら絶対に宇治のためになると思うし、宇治に引っ越してしまった私自身も幸せになれるから、というようなことを訴えていました。すると、「いや、やってくださいじゃなくて、自分でやったらいいよ」と背中をドーンと押されたんです。「やっていいの、私が?」と、びっくりしました。まさか自分がシェア型書店をやれる、作るとは思っていなかったんですけど、「そっか、やったらいいやん!やってみるか!」って、すぐに決意しました。
石津:そして物件探しがはじまるわけですね。初めに予定していた物件の交渉を、途中で断念せざるを得なくなるなど紆余曲折もありましたが、うじらぼやQUESTIONで培ったコミュニティの皆さんから、助言もいただきながら進めておられましたよね。
山本:そうですね。最初に決めていた物件がダメになってからも、インターネットで探し続けて、本当にたくさんの不動産会社に連絡を入れて、内覧もたくさんして、ようやくここを見つけました。内覧が可能になる日はまだだいぶ先だったんですけど、もう待ちきれなくて不動産会社さんにアタックして大家さんに繋いでいただいたんです。不動産会社の担当の方はすごく理解があってスピード感もある方でした。「こういう事業だったらきっとこちらの大家さんは理解してくれると思います」と前向きに話を進め、協力してくださったんです。
石津:事業を始めるための補助金申請の支援は、当金庫 宇治支店にサポートをお願いしました。支店長の川嶌さんは奈々さんのことをすでにご存じで、「山本さんのことやったらよく知っているよ」と、快く相談に乗ってくださいました。奈々さんを担当されたのが望月さんですが、当時のことを教えていただけますか。

望月:山本さんに初めてオンラインで事業のお話を伺ったときは、シェア型書店がそもそもどんなビジネスモデルなのかあんまりピンときませんでした。融資するとなると事業計画が必要になります。箱主さんが何人集まるかによって売上が決まるので、そこをどう見積もって計画していくのか、実際に山本さんとお会いしてしっかりお話して、自分なりに考えていきました。山本さんは地域のいろんなコミュニティに入って、いろんな人と繋がっておられたので、その辺りを考慮に入れながら事業計画を一緒に作っていきました。
石津:事業体としてどうやって収益を得るのか、損益分岐は、みたいな話をずっと奈々さん、望月さん、宇治市の皆さんとでお話させてもらっていました。小松原さんは奈々さんのこの一連の活動や起業をどのようにご覧になっていますか。

小松原:奈々さんには2年前から創業に関するセミナーやたくさんの事業にご参加いただいていまして、今年の創業支援補助金にいよいよご応募いただいたことは感慨深いです。これまで我々がやってきた創業機運醸成の活動が結実しようとしていることは、ありがたいなと思います。起業家など宇治で活動する方々と多く交流をしてもらい、最終的に宇治でHONBAKOを開いていただいて、良い事例をつくっていただいて感謝しています。奈々さん自身も幸せになってほしいなと思っています。
山本:はい。今、私は毎日大好きな宇治で大好きなHONBAKOに毎日通うことができて、毎日が日曜日のようです。

山本:引っ越してきて驚いたことの一つは、宇治市の職員さんたちが市民に近い立場にいてくださるということです。 普段宇治で暮らしていて市民として感じていることや、こんなことをやりたいという話が気軽にできて、それを「うんうん」って根気強く聞いてくれる行政の人がいる、すごい!と。京信さんに至っては「えっ、これが本当に金融機関なの?」と思いました。石津さんみたいなコミュニティマネージャーという肩書きの人が、金融マンの中にいるということもすごく驚きました。QUESTIONで開かれるイベントや行事ごとも、自分が思い描いていた金融機関とは全然違っていて毎回とても楽しかったんです。
望月:宇治市さんとQUESTIONが連携して、宇治支店が加わったという流れになるんですが、いち営業担当者が日常的に宇治市さんと連絡を取り合うことはなかなか難しい面もあるので、今回QUESTIONの石津さんに間に入ってもらったことで、スムーズに進めることができたと思います。
山本:宇治市じゃなかったら、京信さんじゃなかったら、こういうシェア型書店というコミュニティビジネスはきっと実現しなかったか、もっともっと時間がかかってたんじゃないかなと思っています。
クラウドファンディングは自分の持つつながりの外にも間口が開いている。

石津:さて、3月27日から始まったシェア型書店HONBAKO京都宇治のクラウドファンディングですが、スタートして4月29日まで約1ヶ月間続きますね。クラウドファンディングをやろうと思ったのはどうしてでしょう。
山本:お金を集めるというよりは箱主さんを一斉に募集できるという告知のほうが主目的ですね。あと、私はこの1年半いろんなところでシェア型書店HONBAKOを宇治に作ると発言してきました。QUESTIONやうじらぼで「応援するよ」と言ってくださった方が、クラウドファンディングでなら応援していただけるかな、と。
石津:堺のHONBAKOさんがクラウドファンディングのCAMPFIREのパートナーですから知見もありますしね。クラウドファンディングのページの奈々さんの文章、密度が濃くて思いがしっかり伝わってきます。
山本:事業計画書を作るときに頑張って文章を書いたのが活きましたね(笑)
石津:クラウドファンディングはまだ終わっていないですが、今の時点でやって良かったなって思う点はありますか。
山本:今まで出会った方と私のことを知っている人だけが支援してくれるものなのかなって予想していたのですが、実際にご支援くださった方を見てみると、私が全然知らなかった方も多く、シェア型書店や本屋さんが宇治にできることを楽しみに待ってくれていたんだと分かりました。クラウドファンディングは、自分がインスタグラムやFacebookのようなSNSで繋がっていなかった人たちにも間口が広がるんだなと思いました。
石津:クラウドファンディングを通じて、これまで出会ってこなかった人たちとの出会いがあったんですね。
山本:はい。たくさんありました。クラウドファンディングの仕組みに慣れてない世代の方がここにお見えになって、慣れている世代の方がクラウドファンディングのやり方を教えてくださるんですよね。既に箱主さん同士の交流がここで少しずつ生まれていることがすごく嬉しいです。
 シェア型書店HONBAKO京都宇治の2階はミニキッチン併設の「シェアスペース」になっており、箱主さんが本箱の中だけでは伝えきれない想いや表現を、セミナーやワークショップなどのイベントを通じて本箱を拡張するように利用することができます。また、契約プランにもよりますが、箱主さん自身が本以外の商品を店内で販売できる「お店番」ができるメリットもあり、本を販売するだけでない、箱主さんの自己表現を広げる場として、HONBAKOを活用してもらいたいという山本さんの思いが込められています。
シェア型書店HONBAKO京都宇治の2階はミニキッチン併設の「シェアスペース」になっており、箱主さんが本箱の中だけでは伝えきれない想いや表現を、セミナーやワークショップなどのイベントを通じて本箱を拡張するように利用することができます。また、契約プランにもよりますが、箱主さん自身が本以外の商品を店内で販売できる「お店番」ができるメリットもあり、本を販売するだけでない、箱主さんの自己表現を広げる場として、HONBAKOを活用してもらいたいという山本さんの思いが込められています。シェア型書店HONBAKOが宇治を訪れる人の目的地になれたら。

石津:このHONBAKOについて、これからこんな姿になったらいいなっていう思い描いている理想はありますか。
山本:HONBAKOに関わる人、出入りする人たちが、みんな幸せになればいいなって思います。 通える場所があるって安心感がありますよね。ここに来たら誰かに会える、店主の私だけじゃなくて他の箱主さんにも会える。ふらっと出かける場所がある、話せる人がいるって、生活する上で心が豊かになると思っています。そういう場所を目指したいですね。 HONBAKOの箱主さんをやめられないと言ってくださる箱主さんがどんどん増えていくことが理想です。
石津:小松原さんと望月さんからも、HONBAKOに期待したいこととか、こうなってほしいなという思いがあればお聞かせください。
小松原:我々の創業に関するセミナーや補助金といった支援策によって、こうして地域を巻き込んで波及効果を生む事業の開業を後押しできたことは市としても本当にありがたいと思います。また奈々さんがおっしゃったように、ここが地域の人の集まる場所になれば、今度は奈々さんも周りに刺激を与えてくださる存在になるんじゃないかと期待しています。
望月:ここは本を通して人々がフラットに交われるスペースで、いろんな箱主さんが交流をしていくことになると思います。宇治支店にもコミュニティホールがあるので、そこも箱主さんに使ってもらってお互いにイベントをするなど、つながりを持てたらいいなと個人的には期待しています。
石津:宇治支店は課題解決型店舗という12時以降は窓口を閉めて地域と関わりを持ちにいく店舗になりましたので、支店の職員も、奈々さんや小松原さんのような方、そして市民や地域と交わっていけたらいいですね。
望月:私も、ここにふらっと立ち寄って休憩させてほしいです。

山本:もちろんです。HONBAKOは12時からオープンしますので、行政の方や信用金庫の方がお昼休みに来てくださっても全然構わないんですよ。
小松原:そうですね。まずはお客さんとして寄らせてもらいますね。
望月:私も本好きで本屋さんにはよく行くんですけど、買うとなると結構ハードルが高くて、何を選んでいいかわからないんです。この人が紹介してくれる本やったら多分面白いだろうって安心感があれば読みやすくなりそうなので、HONBAKOでお気に入りの箱主さんを見つけたいですね。
石津:まちづくりは根本的にまちに関わっている人とがやるのが本質だと、僕は思っているんですけど、QUESTIONも、面白い人をつなぐとか、引き続きイベントを企画するとか、そんな伴走ができるんちゃうかなと思ってます。信用金庫にとっても、まちづくりへの関わりは重要な役割です。 まちが元気じゃないと信用金庫は元気にならないので、関わる地域の人を増やすお手伝いをしていきたいと思います。
山本:宇治って素敵なところだな、こういう素敵な人たちが集まる場所があるんだなっていうのを宇治以外のところからも認識してもらって、来てもらえるようになればいいなと思っています。シェア型書店HONBAKOが宇治にあるから行ってみようっていうふうに、目的地になったら嬉しいです。

「本を読む人が好き」「読書家の集まる場所は地域の資産になる」という思いを原動力に、大好きな宇治のまちで人と人、想いと想いをつなぐ場を形にした山本さん。
30センチ四方の小さな本箱から心豊かで幸せなコミュニティを宇治に広げる活動はまだ始まったばかり。地域をゆたかにするという志を同じくするQUESTIONも引き続き山本さんのチャレンジを応援しています。
現在、「シェア型書店HONBAKO京都宇治」ではクラウドファンディングを実施中です!
クラウドファンディングはこちら
「歴史ある京都宇治で「シェア型本屋さん」の仲間になりませんか?」
※これより先は株式会社CAMPFIREのWebサイトへリンクします。リンク先の情報につきましては、ご利用者自身の責任の上でご利用ください。
ARTICLES